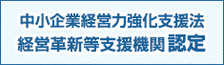所長コラム
江幡淳の税金・経営にまつわる
豆知識シリーズ
2018年03月

2018年03月29日掲載 第019回「税金と選挙権」
日本国民にとって、今では当たり前の権利となった選挙権。総務省のデータによると、平成29年10月に行われた第48回衆議院議員総選挙では、投票率は53.68%だったそうです。
さて、日本で初めての選挙が行なわれたのは、1890年(明治23年)の衆議院議員選挙の時です。ただ、この選挙では、投票できる人は、直接国税を15円以上納めている満25才以上の男性に限られていました。明治23年当時の15円は、現在の価値に換算するといくらになるのでしょうか。単純に物価で比較した場合は、60万円程度とのことですが、1890年頃の政府予算が約1億円、現在の予算規模90兆円の90万分の1ですので、現代の感覚にすれば、年間15円以上の納税者とは、年間1,300万円以上の税金を納めている人達なのではないかという見解があります。
いずれにせよ、明治23年当時の選挙では、日本の全人口の1%の人しか投票できませんでした。
その後、1928年(昭和3年)に法律が変わって納税額により選挙権が制限されることはなくなりました。これにより、全人口の約20%の人が選挙権を持つことになりましたが、依然として女性と25歳未満の男性は投票できませんでした。性別に関係なく、20歳以上の日本人が投票できるようになったのは1946年(昭和21年)からでした。
江幡 淳
「所長コラム 税にまつわる豆知識」 2018 年目次
- 2018年12月15日 第029回「金融実学」
- 2018年11月30日 第028回「商品券と税金」
- 2018年10月15日 第027回「武士の給与と税金」
- 2018年09月27日 第026回「住宅ローン控除と年末調整」
- 2018年08月16日 第025回「酒と税金」
- 2018年07月20日 第024回「源泉徴収の歴史」
- 2018年06月27日 第023回「働く60歳代の方の厚生年金」
- 2018年05月10日 第022回「社員旅行が給料になる!?」
- 2018年04月16日 第021回「皇室と税金」
- 2018年04月02日 第020回「国有地と税金」
- 2018年03月29日 第019回「税金と選挙権」
- 2018年03月05日 第018回「意外と知らない住民税の確定申告」
- 2018年02月14日 第017回「サラリーマンだけど確定申告が必要な人とは?」
- 2018年01月31日 第016回「生命保険と税金」
- 2018年01月24日 第015回「年末調整について復習してみましょう」
無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日